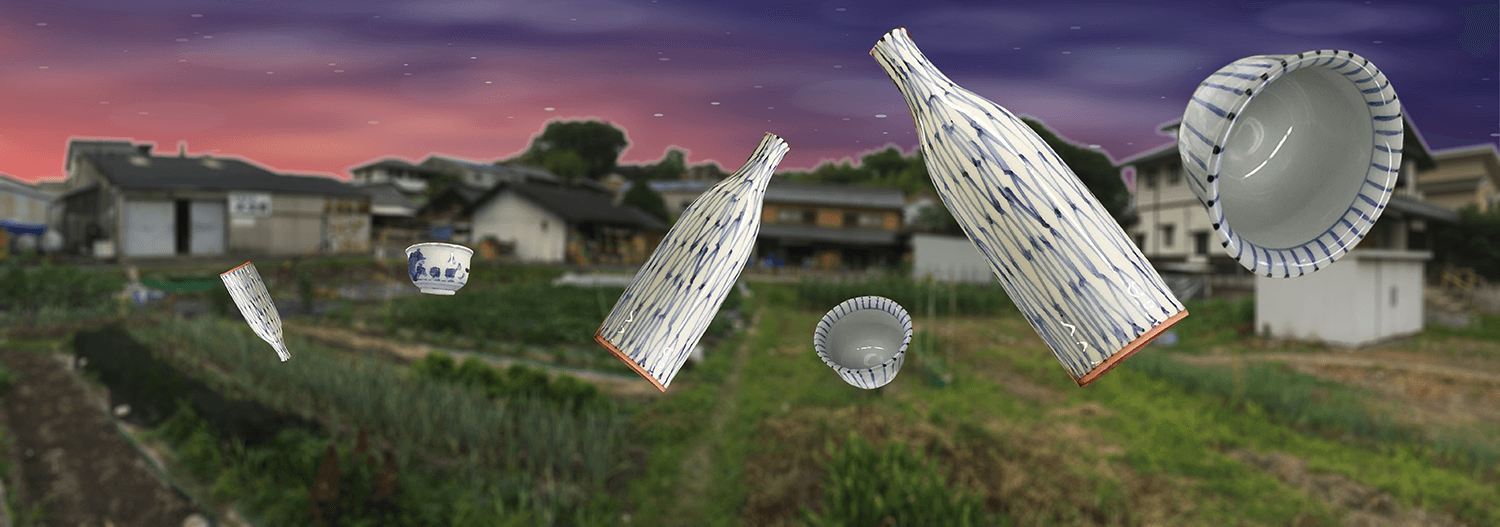これまで陶器を中心に暮らしや食べ物といった様々の観点から多治見市を紹介してきました。やはり多治見は世界最大級の陶器の生産地である美濃地方の一地域であり、陶芸において現在有名な様式のいくつかがここで生まれたのです。多治見の陶芸家のなかには、日本政府から人間国宝として認められた陶芸家が何人もいます。それなのに、こうした事実は海外ではあまり知られていません。
建物の裏には古い登り窯(穴窯)があります。ここでは今でも年に数回焼き物が焼かれています。窯の上に広がる美しい紅葉をご覧ください。
今回は、美濃焼の世界では有名な窯、幸兵衛窯を訪ねました。11月のよく晴れたある日、陶芸家の加藤亮太郎さん(44)がオフィスで迎えてくださいました。速いテンポでハッキリと話す方で、陶芸に対するエネルギーや情熱が伝わってきます。今日加藤さんにお会いしたのは、「ペルシャ・ラスター彩」について、そしてその復興がここ幸兵衛窯から起こったことについて教えていただくためです。本館の2階には、素晴らしいラスター彩が展示された小さく素敵な博物館があります。幸兵衛窯はかつてペルシャにあった芸術様式と強いつながりがあるのです。
幸兵衛窯の本館展示室の一画を写した360°画像
幸兵衛窯元は1804年、多治見の市之倉郷で、美濃の国の初代加藤幸兵衛によって開窯されました。幸兵衛は位の高い人々に食器を染付して納めていました。客のなかには、江戸の大きなお城の領主もいました。亮太郎さんはその七代目の後継者の長男で、美濃地方の復興や、海外における日本陶芸の伝統の認識の高まりに貢献する若い力なのです。その素晴らしい伝統にもかかわらず、幸兵衛窯は海外との取引まだあまり多くなく、現在中国やヨーロッパなどで地位を確立させる取り組みを行っています。それとは対照的に、幸兵衛窯の陶芸家たちは、外国の陶芸文化を日本にもたらしたという重要な役割を果たしてきました。故人間国宝の幸兵衛窯六代目 加藤卓男(1917~2005)は、古代ペルシャのラスター彩陶器に最初に興味を示した人でした。美しい青と3色の釉薬に魅せられ、17世紀以降完全に失われていたペルシャの陶工の技術を復元しようと思い立ちました。
成功に至るまでの道のりは長いものでした。古代のペルシャ人がどのようにラスター彩を作っていたのかに関する情報がなかったからです。ようやく加藤さんは、テヘランのパフラヴィー大学を訪問した際にアメリカ人の故アーサー・アップハム・ポープ教授の研究にめぐり合ういました。ポープ教授は亡くなっていましたが、幸いなことに、夫人がまだご健在で、教授の仕事を日本から来た陶芸家に見せてくれたのです。卓男さんはそのとき、ペルシャ人が使っていた粘土が日本の粘土と異なっていただけでなく、釉薬にも鉛やスズ、ナトリウムなど、東アジアの陶芸の伝統では使われていなかった成分が含まれていたことに気づきました。さらに、ラスター彩用の窯は小さく、一度に数個しか収められないようなサイズの窯で、焼成温度はかなり低く保たれなければならなかったのです。
「発見のなかで最も重要だったのは」と亮太郎さんは説明します。「ペルシャ窯の建造技術でした。炎が直接陶器に触れないように設計されていたそうです。ポープ教授の研究のおかげで、釉薬の中の金属酸化物と窯の独特の設計の組み合わせによって、古代ペルシャ人はラスター彩を作ることができていたことが分かり、卓男さんは本格的に探究を進めることができました。この大きな謎を解くためのパズルには、たくさんの鍵がありました。ペルシャ人によって使用された粘土は、ここの粘土とは成分が違います。ペルシャの粘土には塩分やマグネシウムが大量に含まれており、それによって陶器は壊れやすくなります。また、日本の粘土よりも耐熱性に劣り、高温で焼くとバラバラになり、溶けてしまいます。そのため通常、日本や中国では摂氏1200°で焼くものが、ペルシャでは900°という低温に保たなければなりませんでした。とにかく、ペルシャ・ラスター彩は壊れやすいのです。」
これを説明するために、亮太郎さんは棚から古代のものと思われる陶器の破片を持ってきて私に見せながら説明してくれました。
これを説明するために、亮太郎さんは棚から古代のものと思われる陶器の破片を持ってきて私に見せながら説明してくれました。
「ご覧いただけるように、これは壊れているでしょう。現在発見されるラスター彩のほとんどが壊れています。卓男はイランの粘土を家に持ち帰り、古典的なペルシャ陶器を再現しようとしましたが、失敗しました。それからまもなく、この地元の粘土を使うようになりました。そうしてはるかに丈夫な陶器を作り出すことができました。ただ施釉はペルシャのやり方に従って行いましたから、最終的な結果はハイブリッドなものでした。だからこそ、私たちが作るラスター彩は丈夫なのです。」
彼はさらに説明を続けます。「ラスター彩の何が特別かと言うと、見る者の視角によって色が変わるところです。光を美しく反射しますが、こんなふうに光を反射できる陶器を作り出すのは大変なのです。焼成が失敗すると、焼き上がった陶器はまったく艶のないものになってしまいます。焼く度に陶器のほとんどが失敗に終わってしまうのです。」
彼はまたこのように説明を続けました。「イランと日本の違いでもう一つ重要なのは、湿度です。イランの気候はとても乾燥しています。砂漠の気候なので、ラスター彩の製作には最適です。対照的に、日本はたいへん湿気の多いところです。雨の日には焼成が失敗することもよくあります。そのうえラスター彩用の窯は小さくなければいけませんから、生産量が少ないのです。これと焼成の失敗の数が多いことから、ラスター彩を食器といった大規模な市場用に生産するのはコストが合わないのです。」
「卓男さんはこのペルシャ陶器の青色に一目ぼれされたんですよね、でもそれはどんな青なんですか?」と私は尋ねてみました。
「ああ、ペルシャン・ブルーですよ。」亮太郎さんはそう言ってまた別の陶器を持ってきてくれました。
「ご覧いただけるように、これは壊れているでしょう。現在発見されるラスター彩のほとんどが壊れています。卓男はイランの粘土を家に持ち帰り、古典的なペルシャ陶器を再現しようとしましたが、失敗しました。それからまもなく、この地元の粘土を使うようになりました。そうしてはるかに丈夫な陶器を作り出すことができました。ただ施釉はペルシャのやり方に従って行いましたから、最終的な結果はハイブリッドなものでした。だからこそ、私たちが作るラスター彩は丈夫なのです。」
彼はさらに説明を続けます。「ラスター彩の何が特別かと言うと、見る者の視角によって色が変わるところです。光を美しく反射しますが、こんなふうに光を反射できる陶器を作り出すのは大変なのです。焼成が失敗すると、焼き上がった陶器はまったく艶のないものになってしまいます。焼く度に陶器のほとんどが失敗に終わってしまうのです。」
彼はまたこのように説明を続けました。「イランと日本の違いでもう一つ重要なのは、湿度です。イランの気候はとても乾燥しています。砂漠の気候なので、ラスター彩の製作には最適です。対照的に、日本はたいへん湿気の多いところです。雨の日には焼成が失敗することもよくあります。そのうえラスター彩用の窯は小さくなければいけませんから、生産量が少ないのです。これと焼成の失敗の数が多いことから、ラスター彩を食器といった大規模な市場用に生産するのはコストが合わないのです。」
「卓男さんはこのペルシャ陶器の青色に一目ぼれされたんですよね、でもそれはどんな青なんですか?」と私は尋ねてみました。
「ああ、ペルシャン・ブルーですよ。」亮太郎さんはそう言ってまた別の陶器を持ってきてくれました。
「これも古い焼き物です」と亮太郎さん。「この種の釉薬は大変古く、銅を加えることによってこの青色が得られると言われています。とても簡単な技法なのですが、中国にはこれに相当するものはありませんでした。その一方で、エジプトのファラオの墓からはこの種の青の陶器が数多く発見されています。メソポタミア人もこの種の陶器を作っていました。この地域では一般的だったようです。砂漠の世界で心に浮かぶ生命のイメージとは水の青色だったのだろう、と簡単にに想像できますよね。」
「こちらの陶器の青は?」最初に見せてくれた陶器の方を指さして尋ねました。
亮太郎さんは「これはこの釉薬の中のコバルトの効果です。この種の色は中国でも作られていました。陶器に関しては中東と中国が最古の生産地域であり、両地域はシルクロードによって結ばれていました。そのため交流の機会はたくさんあったと考えられます。ペルシャン・ブルーについて、そういった陶器は中国で発見されてはいますが、中国人が自ら製作したことは一度もないようなのです。ただ緑の陶器は作られていました。」
彼は緑の焼き物を持ってきてくれました。「これは中国で作られたものですが、同じ種類の陶器がペルシャでも生産されていました。興味深いことに、銅はまた、緑色を作り出すためにも使われていたんです。釉薬の成分によって、色がこんなふうに変わるのです。」
「3色の釉薬は?」と気になりました。
「そうですね、それが日本語で三彩と呼ばれるものです、」と亮太郎さんは答え、再び別の見本を持ってきてくれました。 「これは古代中国のものです。三彩は通常は緑、黄、白です。これは8世紀のものです。この技法はペルシャに移り、ペルシャ三彩になりました。それが日本にもたらされたときには、七彩に発展していました。こういった技法が大陸を越えるにつれて、異なった地域で様々なバリエーションが発展していきました。釉薬のスペクトルも広がったのです。」
「今日、イランとの交流はどうなっていますか?」
「当時イラン大使だったセイエッド・アッバス・アラグチ博士が、私どものラスター彩のことを聞いて訪問してくださいました(アラグチ博士は2008~2011年にイラン大使として赴任)。博士には大変喜んでいただき、自国とのこの交流は拡げるべきだとおっしゃいました。父と私はイランを訪れ、イラン国立博物館で展覧会を行いました。その展覧会のハイライトは父の作品でしたが、卓男の陶器も古代や現代のイランの作品とともに展示されました。」
「私が展示を担当し、やり方に文化の違いはありましたが、なんとかうまくいきました。大変好評で、イラン側と私たちの間でさらなる交流についての話し合いが始まりました。イランは13世紀にモンゴル人に侵略され、窯はモンゴル人に破壊されてしまいました。ラスター彩の文化は17世紀までにはイランからすっかり消えてしまったのです。卓男が復元したことによって初めて、この芸術様式は再び脚光を浴びるようになったのです。イランの若い陶芸家たちは卓男の努力に感銘を受け、触発されて自分で製作を始めるようになった方も何人かいます。2年前には2人の陶芸家がここに来て、3か月間滞在し、様々な技法を学んでいきました。来年もう2人予定されていますので、交換はずっと続いています。習得するのが大変難しい技能ですが、私どもには異なるアプローチがあります。そしてイランの方々には当然のことながら元来の方法に戻って復活させたい伝統があるのです。ですがこの交流は有意義だと思っており、もっと発展させることができれば、と楽しみにしています。」
幸兵衛窯の陶芸家の方々はペルシャ陶器の復活に大きく貢献されてきましたが、亮太郎さんは今度は美濃焼を復興させたいと考えています。
「織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった有名な武将や千利休といった茶人は、この土地の陶器の歴史の一部でもあります。私は今、こうした歴史上の人物が使っていた茶道具の製作に取り組んでいます。桃山時代に入るまでには、美濃では陶器が黄金時代を迎え、日本の陶芸の重要な様式がここで生まれました。次の世代の陶芸家はこの伝統を再開させなければならないと思っています。若い陶芸家の大半が現代陶芸をやりたいと思っていますが、一番いいのは、伝統的な陶器と現代風のデザインを合わせることだと思うのです。私は大学時代を京都で過ごしましたが、ここに戻ってきて、美濃にあるものはとても特別なものなんだ、ということにあらためて気がついたのです。」
彼は緑の焼き物を持ってきてくれました。「これは中国で作られたものですが、同じ種類の陶器がペルシャでも生産されていました。興味深いことに、銅はまた、緑色を作り出すためにも使われていたんです。釉薬の成分によって、色がこんなふうに変わるのです。」
「3色の釉薬は?」と気になりました。
「そうですね、それが日本語で三彩と呼ばれるものです、」と亮太郎さんは答え、再び別の見本を持ってきてくれました。 「これは古代中国のものです。三彩は通常は緑、黄、白です。これは8世紀のものです。この技法はペルシャに移り、ペルシャ三彩になりました。それが日本にもたらされたときには、七彩に発展していました。こういった技法が大陸を越えるにつれて、異なった地域で様々なバリエーションが発展していきました。釉薬のスペクトルも広がったのです。」
「今日、イランとの交流はどうなっていますか?」
「当時イラン大使だったセイエッド・アッバス・アラグチ博士が、私どものラスター彩のことを聞いて訪問してくださいました(アラグチ博士は2008~2011年にイラン大使として赴任)。博士には大変喜んでいただき、自国とのこの交流は拡げるべきだとおっしゃいました。父と私はイランを訪れ、イラン国立博物館で展覧会を行いました。その展覧会のハイライトは父の作品でしたが、卓男の陶器も古代や現代のイランの作品とともに展示されました。」
「私が展示を担当し、やり方に文化の違いはありましたが、なんとかうまくいきました。大変好評で、イラン側と私たちの間でさらなる交流についての話し合いが始まりました。イランは13世紀にモンゴル人に侵略され、窯はモンゴル人に破壊されてしまいました。ラスター彩の文化は17世紀までにはイランからすっかり消えてしまったのです。卓男が復元したことによって初めて、この芸術様式は再び脚光を浴びるようになったのです。イランの若い陶芸家たちは卓男の努力に感銘を受け、触発されて自分で製作を始めるようになった方も何人かいます。2年前には2人の陶芸家がここに来て、3か月間滞在し、様々な技法を学んでいきました。来年もう2人予定されていますので、交換はずっと続いています。習得するのが大変難しい技能ですが、私どもには異なるアプローチがあります。そしてイランの方々には当然のことながら元来の方法に戻って復活させたい伝統があるのです。ですがこの交流は有意義だと思っており、もっと発展させることができれば、と楽しみにしています。」
幸兵衛窯の陶芸家の方々はペルシャ陶器の復活に大きく貢献されてきましたが、亮太郎さんは今度は美濃焼を復興させたいと考えています。
「織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった有名な武将や千利休といった茶人は、この土地の陶器の歴史の一部でもあります。私は今、こうした歴史上の人物が使っていた茶道具の製作に取り組んでいます。桃山時代に入るまでには、美濃では陶器が黄金時代を迎え、日本の陶芸の重要な様式がここで生まれました。次の世代の陶芸家はこの伝統を再開させなければならないと思っています。若い陶芸家の大半が現代陶芸をやりたいと思っていますが、一番いいのは、伝統的な陶器と現代風のデザインを合わせることだと思うのです。私は大学時代を京都で過ごしましたが、ここに戻ってきて、美濃にあるものはとても特別なものなんだ、ということにあらためて気がついたのです。」